はじめに:二次試験は一次よりも厳しい壁
中小企業診断士試験の一次試験に合格した皆さん、本当におめでとうございます。長い学習期間を経て7科目を突破できた達成感は格別だと思います。
ただ──油断は禁物です。
診断士試験の本当の勝負はここから。
二次筆記試験は毎年10月に実施されますが、その合格率は例年20%台前半。
一次試験を突破した5人に4人は、この二次試験で落ちてしまいます。
たとえば令和5年度のデータでは、受験者数4,335名に対して合格者は1,087名。合格率はわずか25.1%でした。
一次試験と違い、知識暗記で解ける問題は少なく、答案は“相対評価”で採点されます。
つまり「答案の質」が合否を決めるのです。
そして、多くの人がこう感じています。
- 模範解答を読んでも、自分の答案と何が違うのかわからない
- 予備校の授業を受けているのに、答案の形が整わない
- 80分という制限時間の中で、どう答案をまとめればいいのか全く掴めない
これは決してあなただけの悩みではありません。
むしろ大半の受験生が同じ不安を抱えています。

二次試験で沈む人の3つの共通点
1. 設問解釈を軽視している
設問文は、試験委員が「何を答えてほしいか」を示す最重要の指示書です。
しかし、多くの受験生はここをさらっと読み飛ばし、与件文に飛びついてしまいます。
- 「助言せよ」とあるのに、現状分析だけで終わる
- 「理由を説明せよ」とあるのに、ただの提案を書いてしまう
- 「A社の強みを活かして」と制約があるのに、全く触れていない
これでは点はもらえません。設問解釈を怠ると、答案の方向性がズレたまま最後まで走ってしまいます。
2. 与件文の根拠を拾えていない
与件文は事例企業の経営者が語った「診断材料」です。ここから解答を導くのが鉄則です。
しかし焦っている受験生ほど、自分の知識だけで答案を埋めようとします。
結果、答案は“教科書的に正しいが事例企業には当てはまらない”ものになり、採点者から「与件無視」と判断されてしまいます。
合格者は必ず与件文のキーワードを答案に落とし込みます。
例えば「熟練技術者が高齢化している」という与件があれば、答案には「技能伝承」「若手育成」といった要素が必ず入ります。
3. 時間配分を誤る
二次試験は1事例80分。設問は4〜5問なので、1問あたり使える時間は平均15〜20分です。
不合格者はここで失敗します。
- 与件文の読み込みに30分以上かけてしまい、骨子を作れない
- 答案を書くのを急ぎすぎて論理が飛ぶ
- 最後に時間が足りず、白紙の設問を残してしまう
二次試験は部分点の積み上げで60点を目指す試験。白紙答案があるだけで一気に不利になるのです。
合格者がやっていること──「思考の型」
80分の流れを管理している
合格者の多くは、80分を「設問解釈→与件読み→骨子→答案化」という流れで管理しています。
一例として、以下のような時間配分があります。
- 設問解釈:10分
- 与件文読解:15分
- 骨子作成:20分
- 答案記入:35分
これを繰り返し練習することで、本番でも安定した答案を作れるのです。
設問解釈を丁寧にする
「助言せよ」「理由を説明せよ」「A社の強みを活かして」などの指示を必ず答案に反映させます。
一見シンプルですが、設問とのズレがない答案こそが合格答案です。
与件文から根拠を拾う
答案の各要素は必ず与件文の一文とリンクします。
「誰に/何を/どうやって」の枠で整理し、与件に書かれた事実を盛り込む。
これにより「与件無視」と判定されず、安定して加点されます。
まとめ──不安を安心に変えるために
二次試験は、知識量の多さで勝負が決まる試験ではありません。
むしろ「思考の型を持っているかどうか」で合否が分かれる試験です。
残念ながら、この型は予備校の講義だけでは身につきません。
模範解答を読んで「なるほど」と思っても、自分の答案に反映できないからです。
私自身も最初は不安だらけでしたが、この“型”を取り入れることで答案が安定し、合格ラインを超えることができました。
その具体的なプロセス(80分の分刻みの使い方、設問解釈〜答案化の流れ、実際の再現答案と解説)は、以下の記事で詳しく解説しています。
詳しくはこちら:
【総論編】中小企業診断士二次試験 思考プロセス完全ガイド(note有料記事)
一次を突破した今が、本当のスタートラインです。
合格者が持っている「型」を、ぜひあなたも手に入れてください。


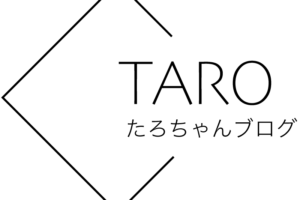
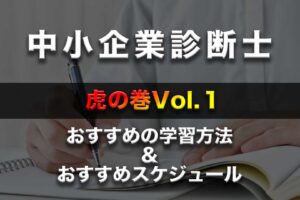
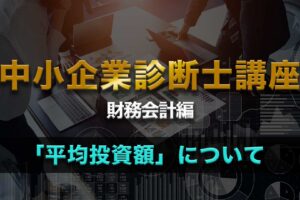
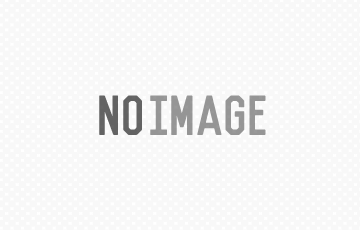
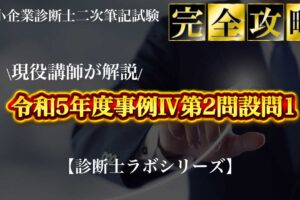
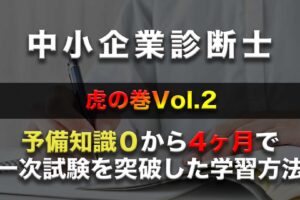
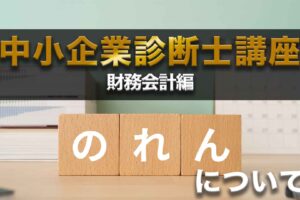
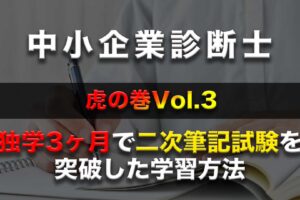

コメントを残す