1.はじめに
「一次試験に合格したけど、二次対策は何もやっていない…」
「残り1か月半で合格なんて無理じゃないか?」
そう思っている方、安心してください。
実は中小企業診断士の二次筆記試験は、一次試験の合格発表後から対策を始めても十分に間に合う試験 です。
なぜなら、二次筆記で問われるのは「膨大な知識量」ではなく、
与件文を使って「答案を組み立てる“型”の再現力」と「持っている知識をどう使いこなすか」だからです。
私は予備知識ゼロから4ヶ月で一次、3ヶ月で二次に合格しました。
そして、通信講座スタディングの講師としても「直前期から始めて合格した受験生」をたくさん見てきました。
この記事では、残り1か月半から合格を狙う最短ロードマップ を具体的に示します。

2.直前期の学習方針(大前提)
「ゼロからでも間に合う」理由は、二次筆記が 知識暗記試験ではない からです。まずは、大前提として理解しておいてほしいポイントを3つ紹介します。
➀新しい知識の詰め込みは不要
一次知識の“主要な部分”は自然と頭に残っています。不安になる気持ちはわかりますが、二次筆記試験に必要な知識は過去問演習をする中で自然と浮き彫りになります。”インプット用の教材”に新たに手を出さないように気を付けましょう。
②やるべきは型の習得だけ
与件を読む → 設問を解釈する → 骨子を作る → 答案を書く。
この手順を体に染み込ませればOK。
この手順については以下の記事で詳しく解説しています。
③目標は60点答案
「80点」や「完璧な答案」を目指す必要はありません。安定して6割取れる答案を目指しましょう。
⇒つまり、残り時間で「型の習得」に全集中すればいいのです。
3.1か月半でやるべきこと
(1) 残り6週間(今〜試験3週間前)
・まずは古い過去問を使って型を練習
直近3年は模試用に残し、4年以上前の問題で「型」の習得を目指します。
事例を解くペースとしては「1日1事例」。
週に5~6事例を解けることが望ましいです(事例Ⅳは除く)。
事例Ⅳは、同友館が出している「30日完成」をとにかくやり込みましょう。
毎日継続することが何よりも大事です。電卓を触って計算の手を止めないことを意識しましょう。
⇒ この時期は「知識を増やす」ではなく「答案作成の練習」という感覚でOKです。
(2) 試験3週間前〜1週間前
・直近2年分を本番形式で解く練習に取り組みましょう。
⇒過去問演習に取り組む際には再現答案を残し、与件根拠が抜けていないか・設問条件を外していないかをチェックすることが重要です。
※過去問演習では「解くこと」よりも「振り返ること」に時間を割くようにしましょう。
・続いて、苦手事例を重点補強していきます。
例えば:
・事例Ⅰ(組織人事):人材育成・動機付けのキーワードを整理
・事例Ⅱ(マーケ):ターゲット・4Pを与件から拾う練習
・事例Ⅲ(生産):工程改善や外注管理の定番ワードを確認
・事例Ⅳ(財務):CVP・NPV・経営分析は必ず解いておく
⇒ 「時間内に答案を形にする練習」を徹底しましょう。
(3) 試験直前1週間
・新しいことはやらない
試験が近づいてくると、不安になっていろんな教材や勉強方法に手を出したくなりますが、付け焼き刃で受かるような試験ではありません。
これまで取り組んできたことを信じて、愚直に繰り返しましょう。
・作り上げてきた型を確認する(読む→解釈→骨子→答案)
二次筆記試験突破の鍵は「再現性」です。
本番でどのような問題が出題されてもある程度のかたちにできるように、「答案作成のプロセス」を今一度確認し、抜け漏れがある場合には補強しましょう。
・生活リズムを試験当日に合わせる(特に朝型にシフト)
意外と見落とされがちですが、夜型の勉強スタイルを継続していると「日中に頭が働かない」ということも珍しくありません。1週間前ほどからは意識的に早寝早起きに取り組み、午前中からお昼にかけて、しっかりと頭が働く環境を整えましょう。
⇒最後の1週間は「仕上げ」ではなく「平常運転の徹底」という意識が重要です。
4.やらなくていいこと
・一次のテキストを最初から復習
冒頭にも書きましたが、二次筆記試験で重要なのは「ただ単に知識を持っていること」ではなく、「知識を使いこなせるかたちにしておくこと」です。そして、二次筆記試験を突破するにあたって「使いこなしたい知識」というのはある程度絞られています。一次のテキストを最初から復習することによって知識を身に付けるのではなく、二次筆記試験の問題演習に取り組む中で「使える知識」や「使える言い回し」「持っておきたい視点」を培っていきましょう。
・模範解答の丸暗記
一次試験でも同じことが言えたかと思いますが、中小企業診断士は「過去に出題された問題が全く同じ形で出題されることはない」試験であるため、模範解答の暗記ははっきり言って無意味です。
・完璧な答案作り
一次試験と同様、「40点未満を取ることなく、平均60点を獲得」することが合格の条件です。100点を取れる完璧な答案を目指すよりも、「多角的な視点から事例企業の課題を捉え、様々な可能性に対応できる再現性の高い答案」を目指しましょう。
⇒今日から始めるなら、無駄な勉強は一切捨てる勇気が大切です。
5.まとめ
二次筆記試験は「知識の量」より「答案作成の型」で勝負が決まります。
つまり、今日からでも1か月半あれば十分に合格可能。
- 過去問を使って型を繰り返す
- 事例Ⅳは毎日少しずつ解く
- 直近年度は模試として時間内にやる
- 新しいことに手を出さず、平常運転を徹底
合格のために必要なのは、特別な才能ではありません。
残り1か月半、迷わずこのロードマップを信じて走り切りましょう。
↓実際の答案プロセスを知りたい方はこちら↓
【完全攻略】現役講師が教える二次筆記試験に“受かる”答案作成プロセス
皆さんが力を出し切れることを心より祈念しております。
ではまた。


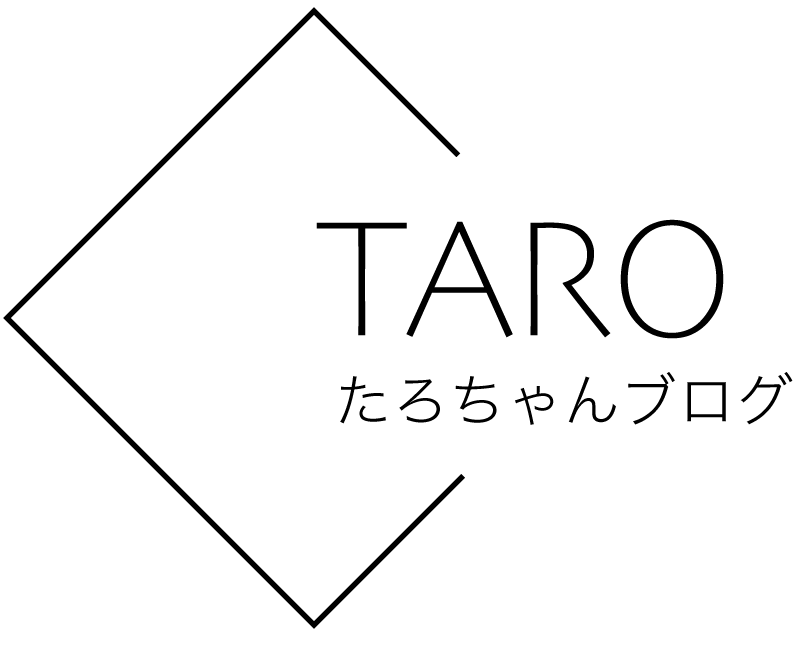
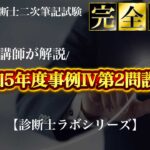
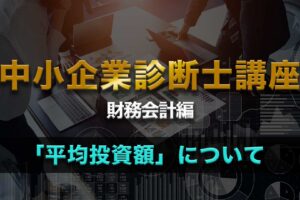
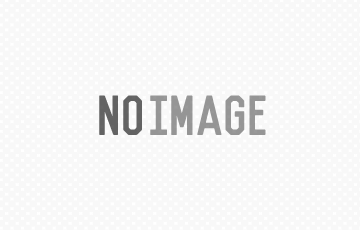


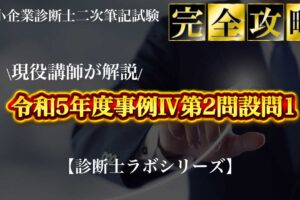
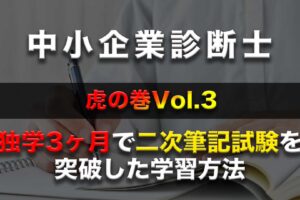
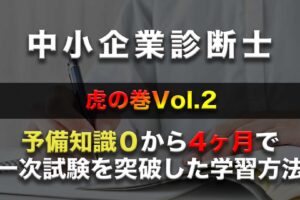
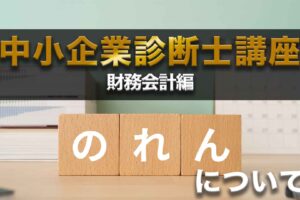

コメントを残す