こんにちは。
わかるようでわからない?!のれんを徹底解説!
たろちゃんです。
このシリーズは、中小企業診断士試験の学習内容についてワンポイント解説をするものとなっています。
私自身が受験生だった頃につまずいた内容や理解が難しかった点などを中心に取り上げて解説しています!取り上げて欲しい内容があれば是非コメント欄で教えてください!
さて今回のテーマは「わかるようでわからない?!のれんを徹底解説!」です。
財務会計を学習していて、「結局”のれん”ってなんなの?」「わかったようでわからないんだけど、どういうときに発生するの?」って思ったことはありませんか?今回はその謎に迫ります!
早速学習していきましょう!
筆者について
- 令和4年度:中小企業診断士試験合格(登録:令和6年6月)
- 令和6年4月:国家資格キャリアコンサルタント試験合格(登録申請中:令和6年5月時点)
<合格までの道のり>
- 令和3年4月:中小企業診断士試験学習開始
- 令和3年8月:中小企業診断士一次試験合格
- 令和3年10月:一次試験に合格した達成感により二次試験会場に行くこともせず棄権
- 令和4年7月:二次試験に向けて学習再開
- 令和4年10月:二次試験(筆記)合格
- 令和5年1月:二次試験(面接)合格
<使用教材>
通信講座:STUDYing
一次試験を4ヶ月で突破した学習方法、二次筆記試験を一発合格した学習方法などについては別途記事を挙げていますので、そちらもあわせてご覧ください!

【中小企業診断士】虎の巻シリーズのバックナンバー
- 【中小企業診断士】虎の巻vol.0(試験概要)
- 【中小企業診断士】虎の巻vol.1(おすすめ教材&スケジュール)
- 【中小企業診断士】虎の巻vol.2(一次試験の学習方法)
- 【中小企業診断士】虎の巻Vol.3(二次試験の学習方法)
「のれん」ってなに?
まずは「のれんの定義」について確認しましょう。
複数のサイトを参考にしてみましたが、以下のようなところでしょうか。
のれんとは、帳簿で測れないブランド価値のこと
買収先となる企業の収益力の高さを評価するもので、一般的には「超過収益力」と定義されており、会計では「のれん」と呼びます。のれんには、ブランド・知名度、人材・組織・社風、技術・ノウハウ、取引先との関係、顧客リストなどのうち、個別の資産として識別できないものが含まれます。
(※M&Aキャピタルパートナーズ様の記事より引用)
これだけだとちょっと難しいですね。
次の項目からもっと具体的に見ていきましょう!
「のれん」を正しく理解しよう!
のれんを理解するには貸借対照表の構造を理解することが重要です。
そもそも貸借対照表はどんなものが記載されるものか整理できていますか?
簡単にいうと、建物や機械といった企業が「お金を稼ぐため」の資産について記載されていますね。
しかし、企業はこれらの建物や機械といった資産だけを頼りにお金を稼いでいるわけではありません。例えば、「ブランド力」や「優秀な従業員」などといった客観的に価値をつけることが難しいものも駆使しながらお金を稼いでいます。
いわゆる目に見えない企業の強みですね。
ところが、この「ブランド力」や「優秀な従業員」については客観的な価値をつけることが難しいので、貸借対照表には記載することができないルールになっています。
これは考えてみれば当然で、例えば「Aさんは営業成績が良いから2,000万円、Bさんは営業成績が振るわないから100万円!」とかつけられてたらすごい嫌ですよね。
自分がBさんだったらショックで会社辞めると思います。
しかし!
「ブランド力」や「優秀な従業員」などといった、客観的な価値をつけることが難しいこれらのものに価値がつけられる瞬間があります。
それが「企業買収」です。
具体例で見てみよう!
前項までで、企業買収のときに「ブランド力」や「優秀な従業員」などといった、客観的な価値をつけることが難しいこれらのものに価値がつけられるということを説明しました。
これを具体例で見ていきましょう!
例えば、「資産:10億円」「負債:5億円」「純資産:5億円」のA社という企業があった場合、資産から負債を差し引いた5億円がA社の純粋な価値となります。

そのA社に対してB社が5億円で買収を提案したところ、「もっと価値がある」として7億円を提示され、B社が7億円の要求を飲み込んだと仮定します。
先ほど見た通り、A社の純粋な価値は5億円だったにも関わらず、実際には7億円で買収が成立するわけなので、貸借対照表上で表せない「2億円のズレ」が生じます。
そこでこの2億円を「のれん」とすることによって帳尻を合わせることになります。

これにより、これまで客観的な価値がつけられないとして貸借対照表上に表されなかった「ブランド力」や「優秀な従業員の存在」に価値がつけられることになります。
これが“のれんの正体”です。
今見てきたように貸借対照表以上の価値があるとして扱い、本来の価値以上の額で買収した際ののれんは「正ののれん」と呼ばれます。
負ののれんとは?
正ののれんがあるということは反対の「負ののれん」も存在します。
負ののれんは、上述の「正ののれん」とは反対のイメージです。
例えば、買収予定の企業が「訴訟のリスクを抱えて」いたり、「経営状況が悪化していたり」するなど、買収にあたってなんらかの懸念事項がある場合には、本来の価値以下で買収できることがあります。
先ほどの例で考えてみましょう。
本来の価値が5億円であるA社を3億円で買収できたとします。
本来5億円支払う必要があったところ、3億円で買収できているため、2億円の乖離が生まれてしまいますね。
この場合は差額の2億円を損益計算書上で「特別利益」として計上します。
これが「負ののれん」です。
お得に企業買収に成功したということですね。

まとめ
いかがだったでしょうか。
今回の記事で少しはのれんへの理解が進みましたか?
のれんは会計を学習する方なら誰もが一度は耳にしたことがあるものの、仕組みを理解するのが難しく、なんとなくの理解で学習を進めてしまっている人が多いのではないかと思います。
ただ、理解することができれば、時折ニュースや新聞で見かける「巨額ののれんを計上!」みたいな記事を楽しみながら読むことができると思います。
中小企業診断士試験は試験範囲が広く、学習が大変ですが、一つ一つ丁寧に理解を進めていきましょう!
取り上げて欲しい論点があればコメントまで!
■あわせて読みたい
【中小企業診断士】虎の巻シリーズのバックナンバー
- 【中小企業診断士】虎の巻vol.0(試験概要)
- 【中小企業診断士】虎の巻vol.1(おすすめ教材&スケジュール)
- 【中小企業診断士】虎の巻vol.2(一次試験の学習方法)
- 【中小企業診断士】虎の巻Vol.3(二次試験の学習方法)
■おすすめ教材
STUDYing


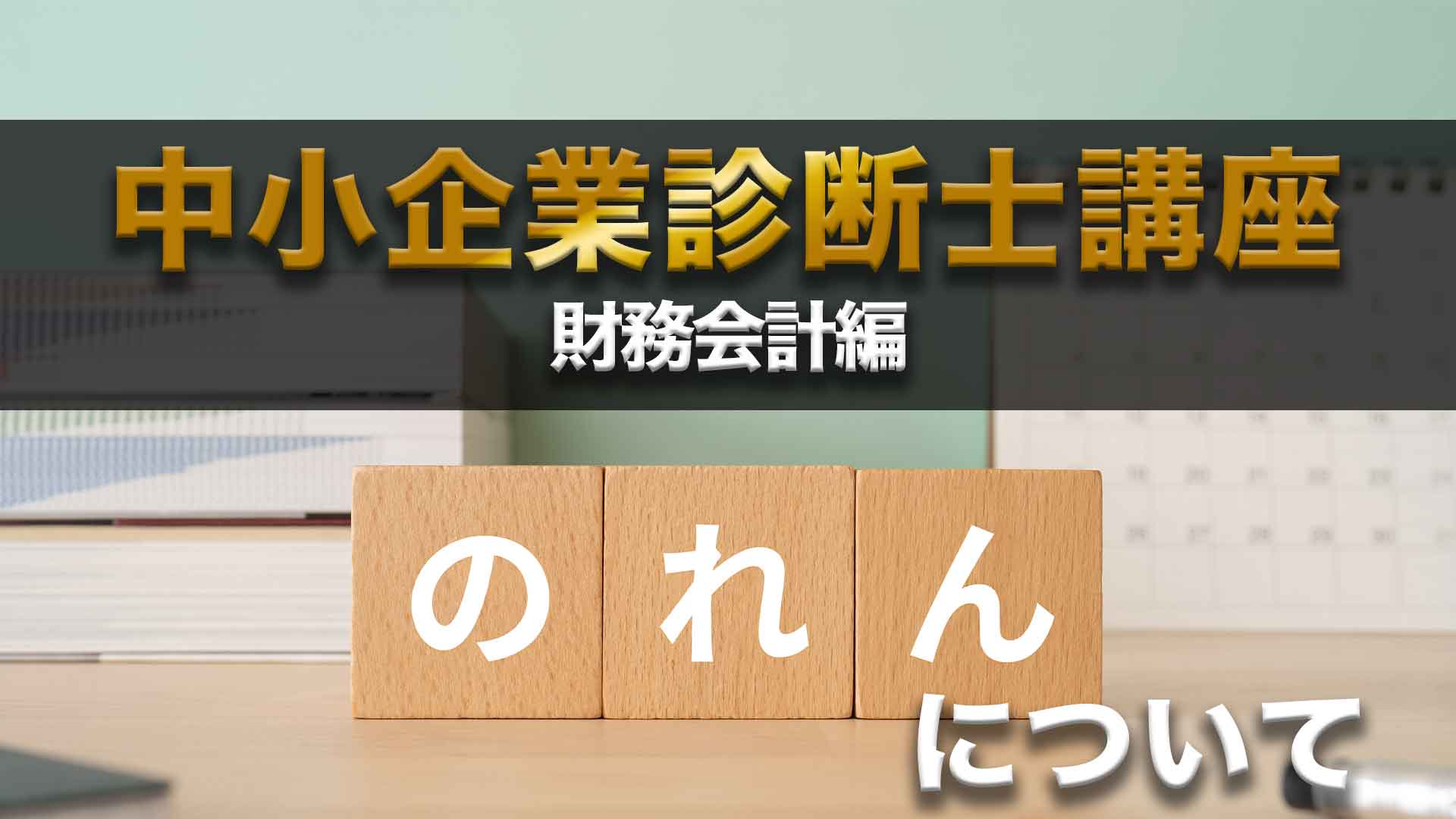

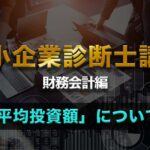
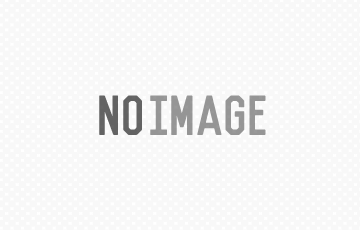
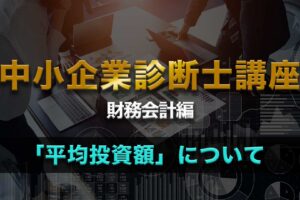

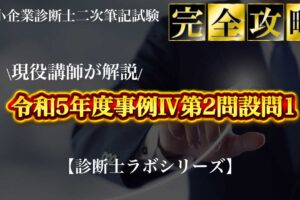

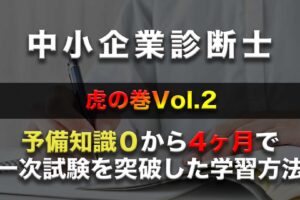


コメントを残す