「変動比率一定=固定費も一定?」の疑問を漫才コンビ「診断士ラボ」が解説!
登場人物紹介

「シンダンくん」
診断士受験に全力投球するけど、ちょっと考えすぎてズレた疑問をぶつけてしまう。
・性格:素直で熱心。

「ハカセ先生」
試験も実務もわかっているベテラン診断士。冷静に突っ込みながら的確に解説。
・性格:落ち着いてるけど時々ちょっと毒舌。

令和5年度事例Ⅳ_第2問設問1
設問文(抜粋)
D社の2期間の財務データからCVP分析を行い、D社の収益性の分析を行う。
原価予測は営業利益の段階まで行い、2期間で変動費率は一定と仮定する。
以上の仮定に基づいてD社の2期間の財務データを用いて、
⑴変動費率および⑵固定費を求め、⑶令和4年度の損益分岐点売上高を計算せよ。
⸻

「先生ぇ〜!令和5年度の事例Ⅳ・第二問なんですけど!解答見たら、“変動比率が一定だから固定費も一定”って書いてたんですよ。
でも僕、思ったんです。
“変動比率と固定費って直接関係なくないですか??”って!
え、もしかして“費用構造が変わらないから固定費も一定”っていうロジックなんですか??」
⸻

「おぉ〜シンダンくん、ええ疑問やな!
でもな、それはズバリ“考えすぎボケ”やで。
変動比率と固定費は全然関係あらへん。
問題文をよう見てみ?こう書いてあるやろ。
『変動費率は一定と仮定する』
『固定費も一定と仮定する』
つまりやな、“両方とも独立した前提条件”ってことや!」
⸻

「え、じゃあ“変動比率が一定だから固定費も一定になる”っていう繋がりはないんですか!?」
⸻

「ないない!繋げたらアカン。
試験では“計算できるように条件を並べてるだけ”や。
・変動比率が一定 → 売上高に対する変動費の割合は変わらない
・固定費が一定 → 人件費とか研究費の水準も変わらない
これは別々の仮定やから、くっつけたら混乱するで。」
⸻

「なるほど〜!じゃあ試験では“そういうもんだ”って割り切って解けばいいんですね!」
⸻

「そうそう!実務やと固定費はステップ的に増えたりもするけど、試験は“問題文の条件に忠実”が鉄則や。考えすぎて減点されるより、サクッと前提を受け入れて計算した方が合格答案に近づくで!」
⸻

「は〜い!じゃあ次からは“与えられた仮定を素直に使う”って心に刻んどきます!」
⸻
【まとめ】
•「変動比率一定」と「固定費一定」は 独立した前提条件。
•試験では「因果関係がある」と考える必要はない。
•実務感覚よりも「問題文に忠実に」が合格の近道。
【診断士ラボ】シリーズでは今後も中小企業診断士試験におけるよくある疑問を対話形式で「易しく、わかりやすく」解説していきます!
◾️おすすめの記事
【完全攻略】現役講師が教える二次筆記試験に”受かる”答案作成プロセス【中小企業診断士/実例付き】


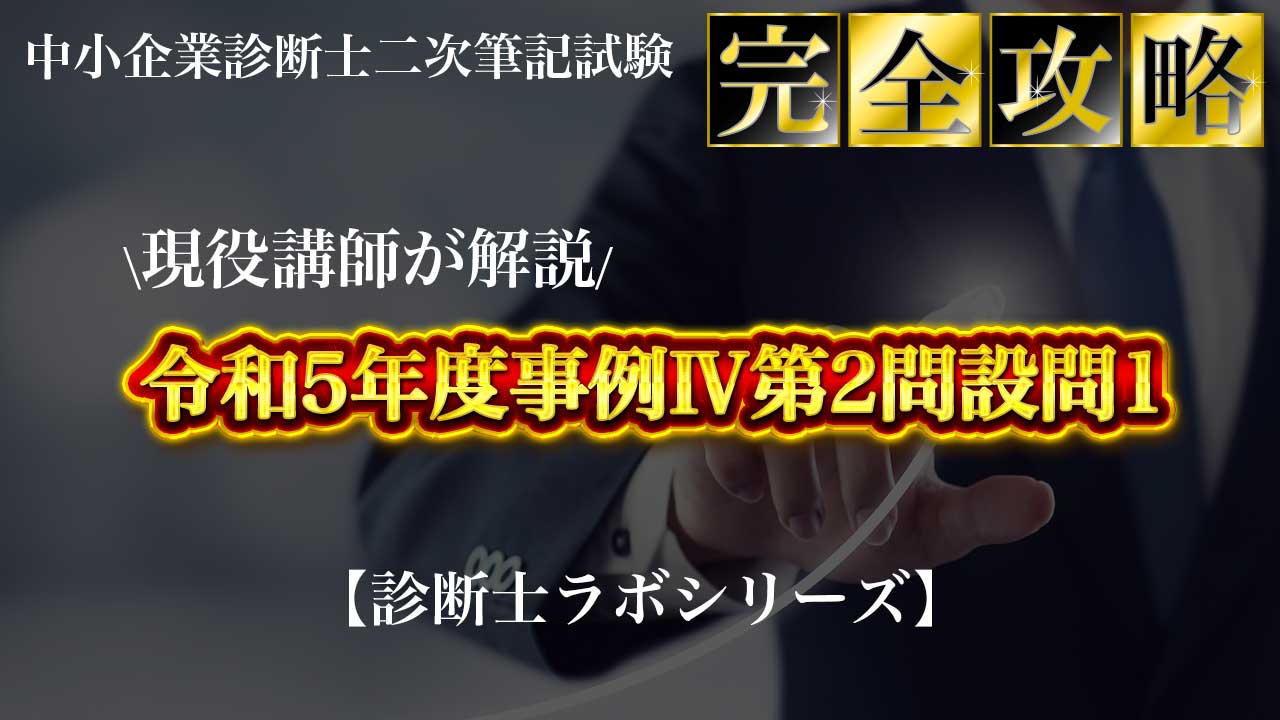
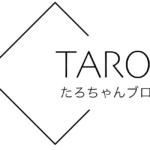

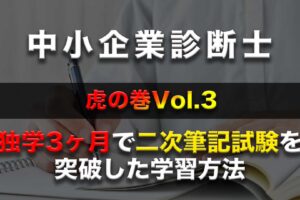
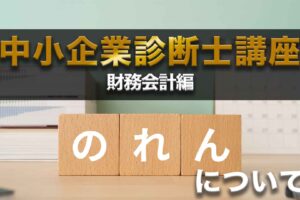

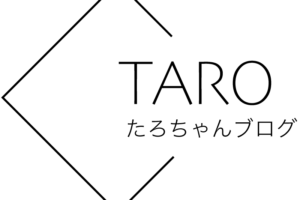
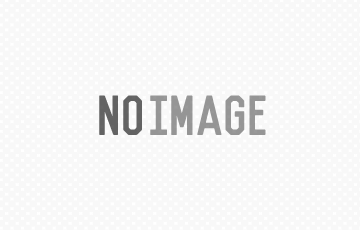
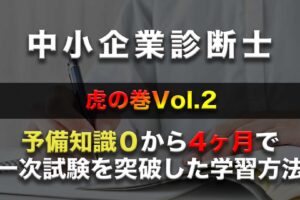


コメントを残す