みなさんこんにちは。
今回は中小企業診断士二次筆記試験の学習方法について、私自身の体験談を交えながら書き進めていきたいと思います。
中小企業診断士の二次筆記試験は採点基準が非公開となっているなど掴みどころがなく、特に独学・半独学者はなにから始めていいかわからないですよね。
私も半独学での挑戦だったので二次試験対策を始める際にはかなり迷いました。
そういった当時の私と同じような不安を抱える方々が勉強方法を確立させる一助となれば幸いです。
この記事を読むと分かること
■中小企業診断士二次筆記試験の学習方法
■二次筆記試験対策の進め方
【中小企業診断士】虎の巻シリーズのバックナンバー
【完全攻略】現役講師が教える二次筆記試験に”受かる”答案作成プロセス【中小企業診断士/実例付き】
筆者の合格までの道のり
まずは簡単に私自身の合格までの道のりを書いておきます。
学習開始時期
R3年4月
学習開始時の保有資格・予備知識
・ビジネス会計検定3級
・診断士試験に関連する予備知識はなし。
目指したきっかけ
金融機関で代理店営業を行なっており中小企業に訪問する機会が多かったため、自社商品のみならず経営周りの知識を持ち合わせていればより良い提案ができるようになると考えたため。
合格までの経路
R3年度に一次試験合格。
もともとストレート合格を目指していたためすぐさま二次試験対策に入ろうとしたが、一次試験合格の達成感・二次対策の難しさから燃え尽き症候群を発症。
結果、圧倒的勉強不足によりR3年度は二次試験会場にすら行かず棄権。
R4年度7月、「そろそろやるか」と重い腰をあげて二次試験対策開始。
一次試験の知識がほとんど抜け落ちており「もっと早めにやってればなぁ…」と思いつつも得意の詰め込み学習で知識の再取得・解法の確立を行う。
結果、R4年度 248点でギリギリ合格。

二次筆記試験対策の進め方
二次試験のポイントをおさらいすると、
・一次試験までのマークシート試験ではなく、論述式の筆記試験。
・各科目、2〜3ページほどに渡ってとある事例企業に関する記述があり、その事例文に隠されたヒント&知識を使って各問80字〜150字ほどで回答する。
・全4科目の記述式試験で合格基準は一次試験と同じく
となります。
二次筆記試験の難しいところが、明確な採点基準が公開されていないということ。そのため、勉強しても目に見えてわかる成果を感じにくくモチベーションの維持も大変難しいというところです。
こんな掴みどころのない試験ですが、筆者は約3ヶ月間の対策でなんとか合格することができました。
今回は筆者おすすめの試験対策についてご紹介したいと思います。この投稿は3分ほどで読めるので診断士試験の受験を考えている方もそうでない方もぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
早速ですが、二次試験対策でのポイントは3点です。
それでは一つずつ解説していきます。
知識を詰め込むことに拘らない
過去問を一度でも解いたことがある方は、
「あー、もう少し知識が頭に入っていれば解けそうなのになぁ」と感じたことがあるのではないでしょうか。
かくいう私もそうでした。
しかしそれは大きな誤りです。
二次試験で求められるのは
「知識を応用して、問題を解決する力」であって、どれだけたくさんの知識を有しているか?ではありません。
よく二次試験の学習に取り掛かる際に「まずは一次試験の知識を完璧にして…」という方がいますが、はっきり言って時間の無駄ですね。
※もちろん実務に取り組む上では一次試験の知識を持っておいて損はないと思いますが、試験に最短ルートで合格することを考えたときには、一次試験の知識を完璧にすることは遠回り以外の何ものでもありません。
とはいえ、一次の知識が全く必要ないのか?と問われると当然そういうわけでもなく、ある程度の知識は必要です。
でも、一次試験の膨大な暗記量に比べれば二次試験で必要な知識量はかなり少ないのです。
重要なのはこの僅かな知識をただ覚えるだけでなく、「どう使いこなすか?」を訓練すること。
つまり、「宝(知識)の持ち腐れ」状態から「使える知識」に変換していく作業が必要になるわけです。
どのようにその作業を行なっていくかについては次のパートで合わせて解説します。
直近3ヵ年分を除き、4年以上前の過去問をひたすら解く
前提として、中小企業診断士試験は一次試験も含めて過去に出題された問題が全く同じ形で再度出題されることはありません。
特に二次試験では、前述した通りとある事例企業に関する事例文を基に回答を作成していくことになるため、仮に過去問と一字一句違わぬ設問が出題されたとしてもその回答内容は当然全く違ったものとなるわけです。
ではなぜ、過去問を解く必要があるのか?
それは「解き方に慣れつつ、必要な知識を素早く身につけるため」です。
二次筆記試験は試験時間80分となっており、その時間の中で2〜3ページほどの与件文を読んで企業概要や課題を把握し、使える知識を引き出し、ロジックを組み立て、回答する。という流れになりますが、解き方を知らずに解こうとすると圧倒的に時間が足りなさすぎます。
そのため、80分間で処理しなければならない一連の手順を、繰り返し過去問を解くことによって身体に染み込ませることが非常に重要になります。
前項では、二次試験で必要とされる能力は、①持っている知識を引き出し、事例企業に当てはめて応用する力である。②必要な知識は一次試験と比べると非常に少ない。ということをお話しました。
次に挙げるのは過去問を解き、復習までしっかり行うことによって得られるメリットですが、上述した「必要とされる能力」2点と見比べていただくと過去問を解くことで二次対策を優位に進められることがお分かりいただけるかと思います。
■過去問に取り組むメリット
①自分の中である程度の回答パターンを構築でき、ロジックの組み立て速度が高まる。
②問題を解くことで不足している知識がどの部分なのかを見極め、復習を行うことで都度その不足知識を補うことができる。
このようにして、過去問を解く⇆参考書等で都度知識補充というサイクルを回すことによって、グッと合格が近づきます。
ちなみに「①ロジックの組み立て」については、STUDYingのロジックマップが非常に役立ちました。診断士試験界隈でもSTUDYingの二次試験合格率の高さは非常に有名なところであり、私自身もかなり助けられました。
繰り返しにはなりますが、診断士試験では過去問がそっくりそのまま出題されることはないので、ロジック・思考フレームを作りあげることで、
「問題によって点数が左右されてしまう。。」ということをなくしていくことがポイントです!
そして、本章のタイトルでは「直近3ヵ年を除く」としてありますが、ある程度試験対策が進み、試験が近づいてきたタイミング(1〜2ヶ月前)で直近年度分の過去問を使ってセルフ模擬試験を行うことをお勧めします。
各予備校の模擬面接を受けることももちろん否定はしませんが、結局のところ作問者が変わると問題傾向もガラリと変わるので、できるだけ過去問で実力を測ることが望ましいと筆者は考えています。
日頃目にするものを100文字〜150字ほどに要約する練習をする
前述の通り二次試験は「論述式」とはいえ、80字〜150字で回答することが多く、1問あたりに書く文字数はそこまで多くはないです。
つまり、短い試験時間の中で「問題の核はどこか?」を見極め、それに対するアプローチを的確に行なっていく必要があります。
元々国語が得意な方であったり、読書好きで文章の本質を見抜くことが得意な方であればこの練習は必要ないかとは思いますが、そうでない方は確実にこの練習に取り組んでおいた方が良いと思います。
やり方は至ってシンプルで、1番オーソドックスなのは新聞に掲載してある春秋を140字以内に要約し、Twitterに投稿する方法です。SNS上でアウトプットしておけばもしかしたらリプなどでフィードバックをもらえるかもしれないですし、同じように診断士を志す方、現役の診断士などの目に留まり、人脈構築に繋がる可能性もあるので、せっかくやるならSNSを活用することをお勧めします。
もしくは試験対策が進み、ある程度の知識が習得ができたら試験に関する知識からテーマを選び、その知識について100字程度で書くのも良いですね。(例えば、「非正規社員を活用することのメリデメを100字で」など。)
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は中小企業診断士二次筆記試験の対策方法についてざっと解説いたしました。今回お話しした内容はあくまでも「概要」にすぎないので、もっと細かな話は今後の投稿で進めていきたいと思います。
ご質問・ご意見などあれば、コメント・メールにて受け付けております。
皆さまが合格に向かって最短ルートで突っ走っていけることを心より祈念しております!
ではまた。
【完全攻略】現役講師が教える二次筆記試験に”受かる”答案作成プロセス【中小企業診断士/実例付き】


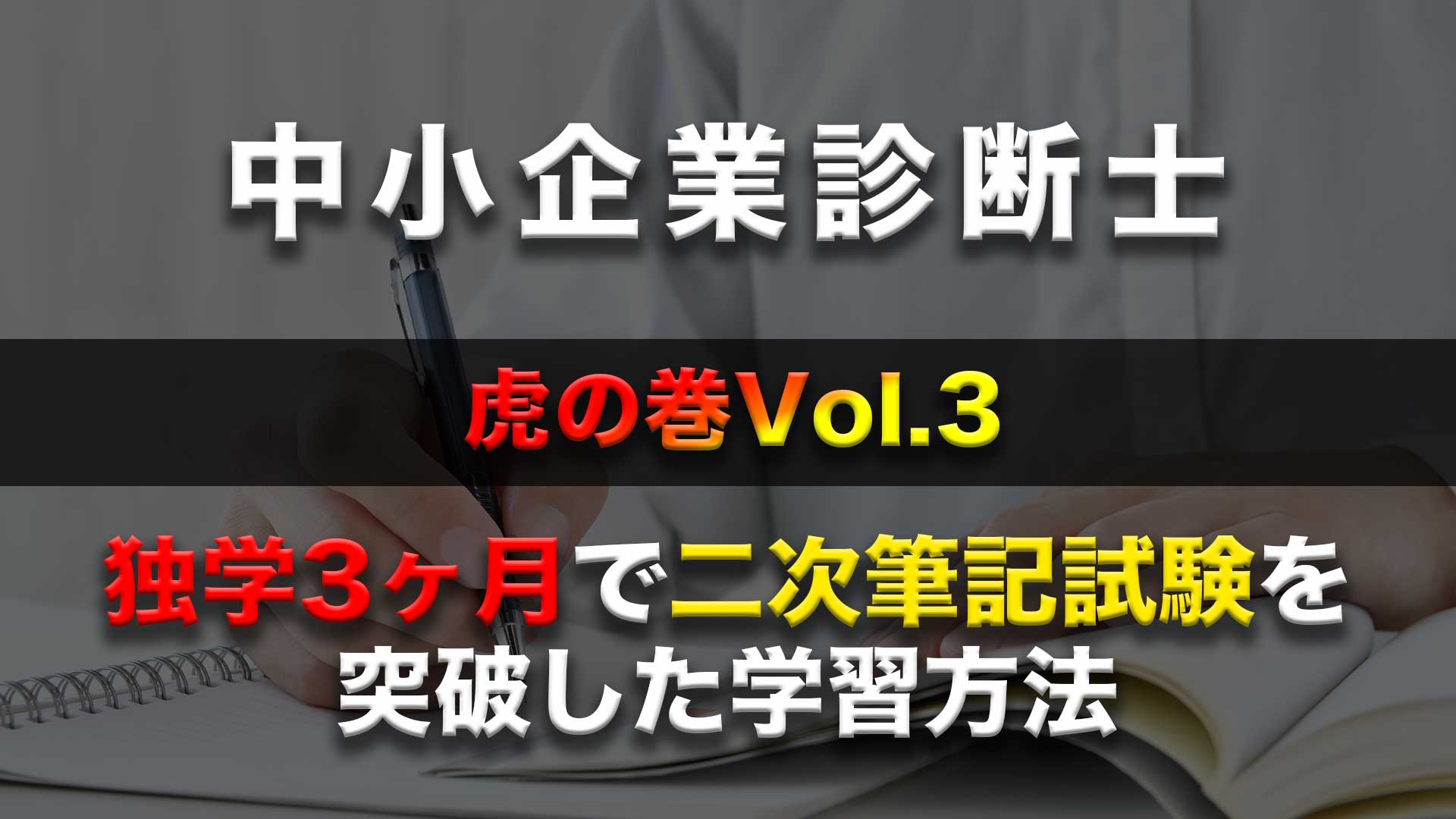
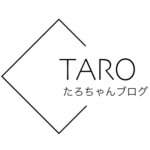
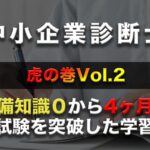
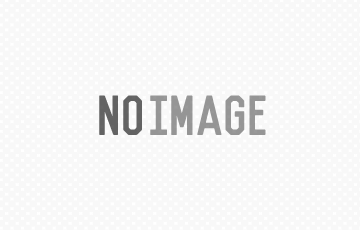
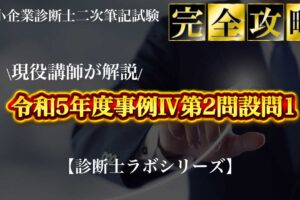
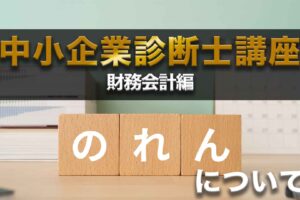


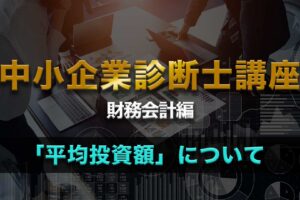

コメントを残す