みなさんこんにちは。
みなさんは「自分なりの物の見方」で物事を考えるのは得意ですか?
私は結構苦手だったのですが、最近わりと得意になってきた気がします。
「自分なりの視点を持ち、自分の意見が言える」ことは、
デジタル化が進んでたくさんの情報に触れられるようになった
現代社会においてかなり重要ではないかなと思います。
そこで今回は「自分なりの物の見方」をテーマに書いていこうと思うので
是非最後まで読んでいただければと思います。
物の見方とアート的思考
突然ですが、みなさんは「アート」は好きですか?
私は好きでも嫌いでもありません。
いや、中学生時代の美術も「アート」に含めるとするならば
嫌いかもしれません。
みなさんの中にも
「小学校までの図工は好きだったけど、
中学校の美術になった途端嫌いになったなぁ」
というかたもいらっしゃるのではないかなと。
なぜ突然こんな話をしたかと言うと、
「自分なりの物の見方」を身につけるためには、
「アート的思考」が重要なのでは?と考えているからです。
アートと聞くとピカソや○○などの有名芸術家のよくわからん絵画(怒られそう)
が思い浮かぶかと思いますが、
彼らのあの「よくわからん絵」が評価されるのは何故なのでしょうか。
何故一見よくわからない絵が評価されるのかということを考えていくと、
アート的思考、ひいては自分なりの物の見方を
身につけるためのヒントを得ることができそうです。
表現の花と探求の根
前述のピカソにはこんな逸話があります。
ピカソが街中を歩いていると見知らぬ女性にこう話しかけられたそうです。
「ピカソさん、私はあなたの大ファンです。
この紙になにか1つ絵を描いてくれませんか?」
ピカソは快く紙を受け取り、ものの30秒ほどで美しい絵をかきあげました。
そして、女性に手渡したあとにこう続けます。
「この絵は100万ドルです。」
女性は驚きました。
「この絵を描くのにたったの30秒しかかかってないんですよ?」
ピカソは微笑んで言いました。
「30年と30秒ですよ」
私たちが絵画鑑賞をするとき、最終的な結果としての「絵」しか
見ることができません。
ゆえに女性も「30秒しかかかってない」と言ってしまったのだと思いますが、
実際にはピカソの言うように、30年間の努力や苦難の賜物が
その30秒に集約されているわけです。
これは花に例えると分かりやすいです。
多くの花は地上に花が咲き、地中には深く根が伸びていますね。
先ほどの逸話で言うとピカソが描いた絵は地上の花にあたり、
30年の努力や苦難は地中に伸びる根っこの部分にあたります。
ここではそれぞれを「表現の花」、「探求の根」と呼ぶことにします。
表現の花は絵のみならず日常生活のあらゆるものに置き換えて
考えることができます。
あなたがなにかに対して述べる意見や
YouTuberが投稿する動画、
この記事も表現の花と呼ぶことができそうですね。
探求の根の重要性
私は、アート的思考を身につけるためには
探求の根を伸ばしていくことが非常に重要だと感じています。
私たちが自分なりの物の見方や自分なりの意見を持てない理由は
この探求の根の弱さにあると考えています。
例えば、なにか仕事を任されたときに
先輩がやっているのを見よう見まねで真似てみたら案外上手く行った。
でも、その経験が特段他の業務に活きている感じはしない。
みたいな経験はありませんか?
見よう見まねでやってみること
さらにはそれで上手くいくことはすごいことです。
では何故、他の業務に活かせないのか?
それは、先輩の表現の花を複製したに過ぎないからです。
ピカソの話で考えれば、
30秒で描いた絵の真似はできたけど、
オリジナルな絵は描けない。のと同じです。
当然といえば当然ですよね。
- なぜそれをやるのか
- なぜそのやり方なのか
- やるとどうなるのか
など、目的や手段を明確にし、
その上で具体的な経験を抽象化することで
応用の効く知識へと転換されていくわけです。
この根っこを育てる作業を怠ってしまうと、
応用が効かない1問1答の花職人になってしまうわけですね。
探求の根の伸ばし方
ここまででなんとなく
「探求の根が大切なんだなぁ」
ということをわかっていただけたかと思います。
が、同時に「それってどうやって鍛えんの?」とも
思っておられるかと思います。
これについては私自身も模索中ではありますが、
現時点で私的には次の2つが大切だと思っています。
- 好奇心を持て
- アウトプットしろ
1つ目に関しては言わずもがなな気もしますが、
いろんなものに好奇心を持って触れてみることで、
確実に知見が広がります。
そしてそれらをアウトプットし、周りの人と共有することで
自分自身の理解を深めるとともに周りからのフィードバックを
得ることが可能です。
ジョブスの「connecting the dots.」ではないですが、
一見何の役にも立たなそうなことでも好奇心の赴くままに
触れてみたら意外なところで他の根っこと繋がったりするものです。
損得勘定に流されず、いろんなものに取り組んでみましょうね!
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は結構抽象的な話になってしまいましたが、
「自分なりの視点」を持つことの重要性とその鍛え方について
お話させていただきました。
話が分かりにくかったという方は、
「探求の根」のことだけでも覚えていただき、
日常生活の中で目に見えないものの存在を
意識してみてください。
きっと、人間関係やコミュニケーションにおいても
役に立つと思いますよ。
もっと詳しくアート思考について知りたいという方は、
こちらの本を是非読んでみてください。
ではまた。
たろちゃん。

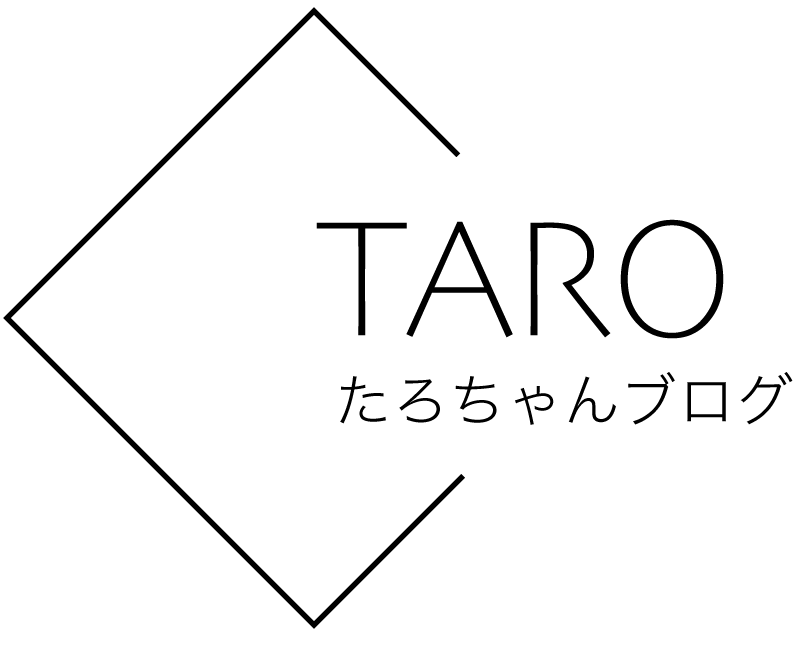





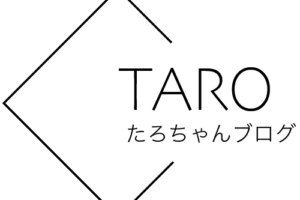


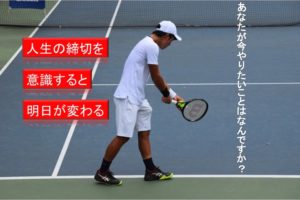

コメントを残す